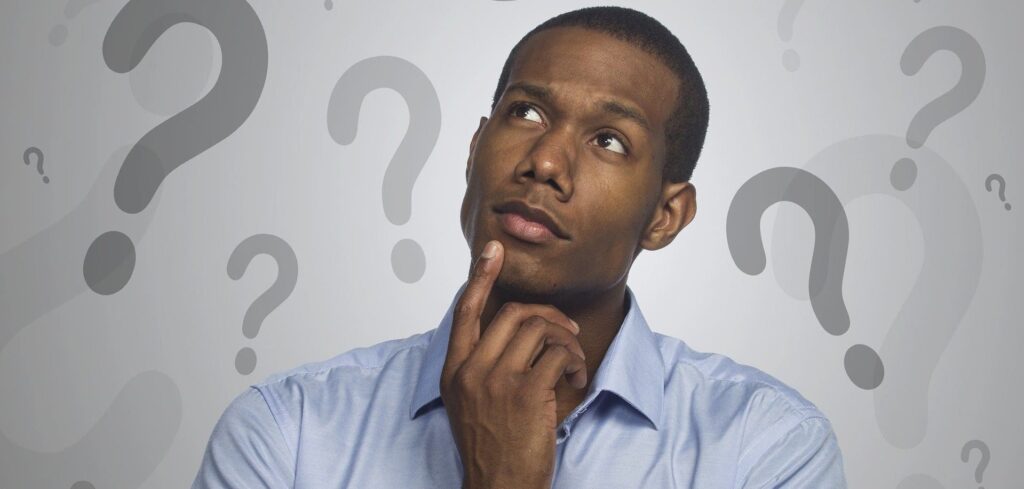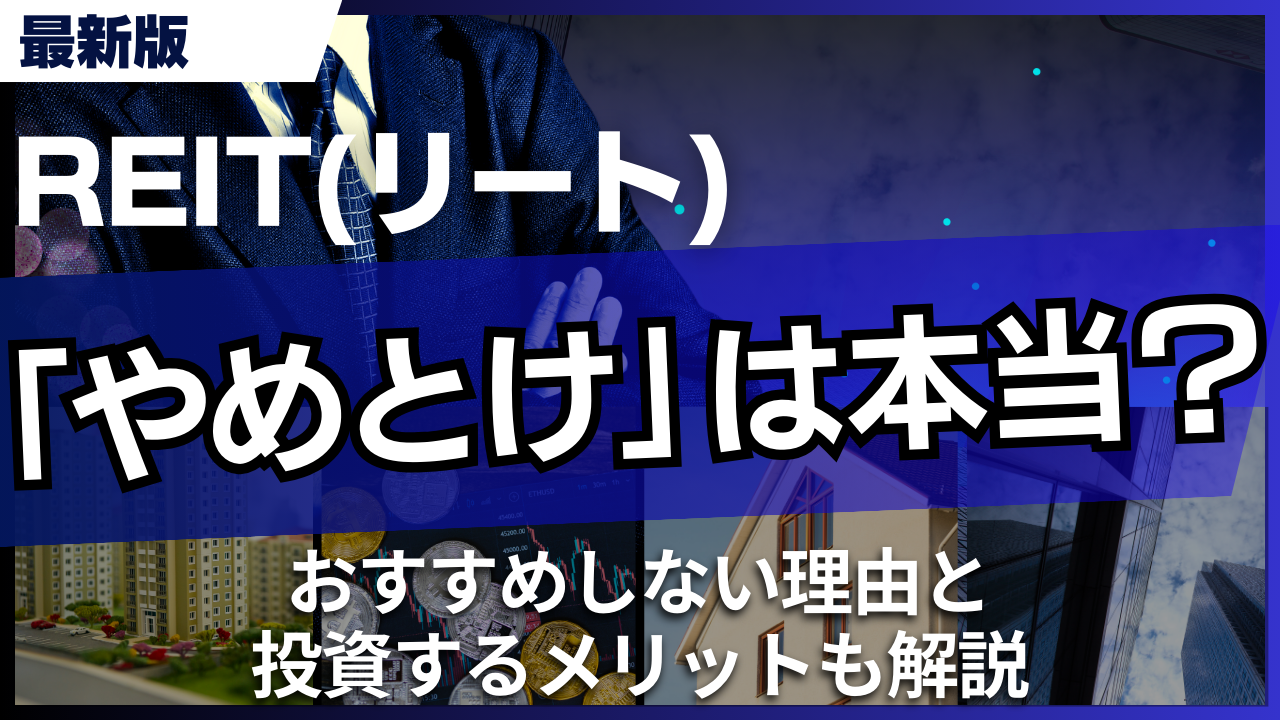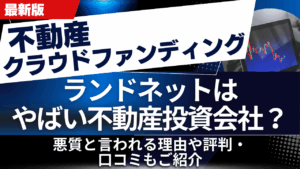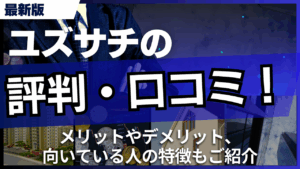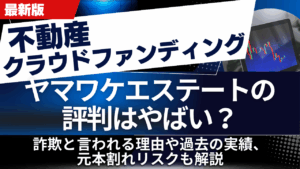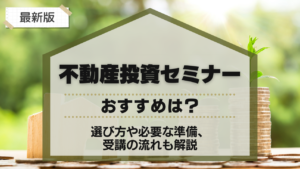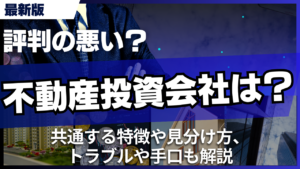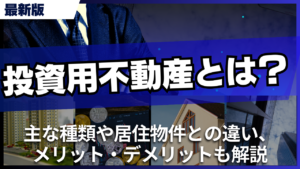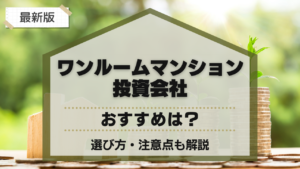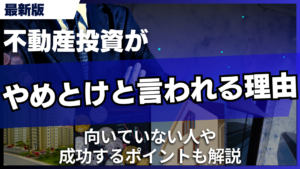- 「REIT(リート)はやめとけ・おすすめしない理由が知りたい」
- 「REIT(リート)に投資するメリットが知りたい」
- 「REIT(リート)が向いている人の特徴が知りたい」
上記のように考えている方は、この記事がおすすめです。
REITは、少額から複数の不動産に対して投資ができるとして、多くの投資家に注目されています。
一方で、REITに対しては「やめとけ」や「おすすめしない」といった、ネガティブな意見が多いのは事実です。
この記事では「REITはやめとけ・おすすめしないと言われる理由からメリット」まで詳しく解説していくため、ぜひ参考にしてください。
- 分配金が変動しやすい
- 元本割れのリスクがある
- レバレッジ効果が得られない
- 複利効果が期待できない
- 信託手数料が発生する
- 分散投資でリスクヘッジの効果は得られる
- 比較的利回りは高い
初回無料WEB面談参加でPayPayポイント50,000円分プレゼント!
月々1万円(※1)から始められる不動産投資RENOSY(リノシー)
\不動産投資売上No.1(※2)/

年収500万円以上の会社員/公務員/医師/士業の方におすすめ
初回無料WEB面談参加でPayPayポイント5万円分貰える!(※)
※上限・条件あり。プレゼント適用条件はRENOSY公式サイトでご確認ください。
※1 返済額、家賃収入、各手数料等、支出と収入との差額について弊社実績から算出。物件やご契約プラン等により異なり、フルローンの場合、別途初期費用として10万円/件が必要です。
※ 東京商工リサーチによる不動産投資の売上実績(2025年3月調べ)
そもそもREIT(リート)とは

REIT(リート)とは、Real Estate Investment Trustの略称であり、アメリカ発祥の投資商品です。
複数の投資家から資金を集め、購入した不動産を運用したうえで、家賃収入や売却益を基に配当を分配する仕組みです。
日本では不動産を対象とした投資信託として知られており、JREIT(ジェイリート)とも呼ばれています。
また、REITは持分(投資口)が証券取引所に上場しているため、一般的な株式と同じように取引が可能です。
一方で、REITは特定目的会社に該当するため、収益の90%以上を分配するなどの要件を満たすことで、法人税が免除されます。
つまり、投資家への積極的な分配が期待できる点も、REITの特徴と言えます。
ここからは、以下に沿ってREITの種類や仕組みをご紹介するため、まずは概要を正しく理解して全体像を把握しましょう。
REIT(リート)の種類
REIT(リート)は不動産の使用用途の数により、大きく分けて以下のように種類分けされています。
- 単一用途特化型のREIT
- 複合型・総合型のREIT
単一用途特化型のREIT
単一用途特化型は、オフィスビル特化や住宅特化など、1つの用途に絞って運用される不動産に対して、投資するREIT(リート)です。
単一用途特化型は、その他のREITに比べて用途が絞られているため、市場の動向が予想しやすい傾向があります。
例えば、オフィスビルやホテルなどは好景気にこそ値上がりしやすいため、比較的予想しやすく分配金だけでなく、値上がり益も期待できるのです。
一方で、単一用途特化型は値動きが比較的激しい分、リターンだけでなくリスクも高いREITです。
特に、今後のマクロ経済では金利上昇が予想されるため、投資対象の不動産用途の見極めが、単一用途特化型のREITでは重要となるでしょう。
複合型・総合型のREIT
複合型や総合型は、単一用途特化型とは異なり、複数の目的で運用される不動産に対して投資するREIT(リート)です。
前項でも触れたように、不動産投資は経済全体の景気と使用用途により、市場価値は大きく変動します。
一方で、複合型や総合型では2つ以上の用途を持つ不動産に対して投資をするため、単一用途特化型に比べて、値動きが少なく市場価値が安定しやすい傾向があります。
値動きが少ない分、得られる配当も単一用途特化型程ではありませんが、リスクヘッジによる安定した分配を求める場合は相性が良いでしょう。
とはいえ、市場の流れによっては不動産業界全体が低迷するケースもあるため、複合型や総合型であれば、必ず安心という訳ではありません。
そのため、リスクリターンのバランスを考慮したうえで、自身が投資すべきREITの種類を見極めると良いでしょう。
REIT(リート)は株式と同じように投資できる
前述した通り、REIT(リート)は証券取引所に持分(投資口)を上場しており、60前後の銘柄があります。
REITは、一般的な株式に該当する投資証券を発行しているため、投資家は株式同様に取引可能です。
また、REITの中には数万円~50万円以上必要な銘柄がありますが、多くは10万円前後で購入できます。
一方で、REITの保有期間中は定期的な配当が期待できますが、購入額に加えて証券会社により定められた、売買手数料が別途必要な点には注意が必要です。
ちなみに、REITでは個別銘柄だけでなく、東証REIT指数に連動した投資信託もあるため、分散投資により、手堅い投資もできるのです。
個別銘柄に比べて手数料が高くなる傾向はありますが、REIT市場全体に対して投資できるため、積み立て投資などにも相性が良いでしょう。
REIT(リート)と他の不動産投資の違い

REIT(リート)への投資を迷っている方の中には、現物不動産投資やソーシャルレンディング、不動産クラウドファンディングなど、他の投資方法も検討している方もいるでしょう。
以下に、REITとその他の不動産投資の違いをまとめましたので、それぞれのメリットデメリットも含め、比較してみてください。
| 投資方法 | メリット | デメリット | REITとの違い | おすすめ記事 |
|---|---|---|---|---|
| 現物不動産投資 | 安定した家賃収入 レバレッジ効果が高い | 管理コストが高い 流動性が低い | 自身が不動産を保有して運用する 買い手が見つかるまで数カ月かかる場合がある | 不動産投資おすすめランキング |
| ソーシャルレンディング | 年利5~10%と高め 複数プロジェクトに分散出資できる | 借り手の破綻による元本割れのリスク 流動性が低い | 投資家ではなく融資者として企業やプロジェクトへ出資 元本に対する利息で利益を得る | ソーシャルレンディングおすすめランキング |
| 不動産クラウドファンディング | 少額で分散投資できる 管理コストが不要 | 募集時の利回りは保証されていない 中途解約できない | プロジェクト単位で資金を集める 流動性が低い | 不動産クラウドファンディングおすすめランキング |
ソーシャルレンディングはやや特殊ですが、上記の通り同じ不動産投資だとしても、REITとはそれぞれ特徴が異なります。
特に、上記全ての不動産投資と比べて、REITは流動性の高さが差別化されている点が分かります。
現物不動産は売却時、新しい買い手が見つかるまで数カ月かかるケースは多々あり、ソーシャルレンディングや不動産クラウドファンディングは、指定期間中の中途解約ができません。
しかし、REITであれば市場にて簡単に取引が可能なため、数日あれば現金化できるのです。
とはいえ、REITを含めどの不動産投資も一長一短あるため、一概に「これが正解」といった答えがある訳ではありません。
「安定した家賃収入が得たい」や「少ない資金で分散投資がしたい」など、自身の投資目的と照らし合わせながら、投資先を慎重に検討しましょう。
REIT(リート)はやめとけ・おすすめしないと言われる理由

REIT(リート)は、少額から不動産投資を始められる点や比較的高い利回り、資産運用の分散性の観点などから、1つの投資先として選ばれることがあります。
一方で、市場の影響で値動きする点や複利効果が得られない点など、投資家にとって不安定要素が多数あるため、ネガティブな意見を持つ方も多いのです。
しかし、現物不動産を運用する程の資金力がない方、株や債券と組み合わせた分散投資の視点から、REITへの投資を真剣に考えている方が多い点もまた事実でしょう。
ここからは、REITを運用するうえでのリスクを以下に沿ってご紹介するため、投資先として検討している方はぜひ参考にしてください。
分配金が市場の影響を受けやすい
REIT(リート)は、3~5%前後の分配金が期待できますが、市場の影響を受けやすい点からやめとけ、おすすめしないと言われています。
例えば、新型コロナウィルスにより観光客が減少した数年間では、ホテル利用を想定した単一用途特化型のREITは、利回りが低下傾向にありました。
また、不動産投資法人の経営状況によっても、分配金の減額が考えられます。
他にも、不動産業界全体の長期低迷や金利上昇に自然災害など、分配金は様々な要素によって変動するのです。
もちろん、複数の不動産に対して投資を行い、リスクヘッジした投資も可能ですが、そもそも不安定さを含むため、やめとけやおすすめしないと言われるのでしょう。
元本割れのリスクがある
REIT(リート)は、不動産の需要と供給バランス、景気や金利をはじめ災害など、様々な要因により日々値動きします。
そのため、売却タイミングを見極めなければ、購入額よりも売却益が低くなり、元本割れを起こしてしまいます。
一時的に売値が下がっているだけなら良いですが、不動産業界全体が下火になっている場合は、長期的に値下がりする可能性もあるのです。
また、万が一倒産や上場廃止に直面すると市場価値は一気に下がるため、元本割れは避けられません。
そのため、改めてREITは元本保証のないリスク商品である点を、念頭に置いたうえでポートフォリオに組み込むか、検討すると良いでしょう。
自然災害により減額のリスクがある
REIT(リート)は、現物不動産に対して投資を行うため、自然災害によって収益が減額するリスクがあります。
自然災害の規模にもよりますが、保有銘柄の物件が特定の地域に集中している場合は、特に注意が必要です。
火災保険や地震保険などにより一定量は補償されますが、銘柄を選ぶ際は対象不動産のエリアについても、慎重に検討しなければならないでしょう。
不動産投資法人の破綻や上場廃止で価値が暴落するリスクがある
REIT(リート)は、投資信託の1つとして不動産投資が可能ですが、運営元の不動産投資法人の破綻、上場廃止により市場価値が一気に暴落するリスクがあります。
例えば証券取引所にて、上場廃止基準に触れていると判断された場合は、REITが監視銘柄に指定され審査などが行われます。
審査により上場廃止が確定すると、1ヵ月の間は整理銘柄に変更となりますが、引き続き売買は可能です。
しかし、監視銘柄や整理銘柄に指定されてしまうと、当然価格が大きく下落するため、買い手が見つからずに、売却益を得られず終わる可能性もあるでしょう。
ちなみに、上場廃止により証券取引所にて売買が出来なくなったとしても、REIT自体は持ち続けられます。
ですが、破綻や清算手続きを行われた場合は、保有していた銘柄の価値がゼロになる可能性がある点は予め理解しておきましょう。
レバレッジ効果が得られない
REIT(リート)は、現物不動産への直接投資に比べて、レバレッジ効果が得られないと言われています。
現物不動産の場合、自己資金が少ない場合でも金融機関から融資を受けて投資できるため、少額であってもレバレッジの効いた運用が可能です。
しかし、REITは株式のような金融商品に分類されるため、担保としての価値が低く、一般的に金融機関側としては融資しない判断を下すのです。
そのため、自己資金以上のレバレッジの効いた投資ができないとして、おすすめしないという方が多いのでしょう。
ちなみに、一部では証券取引所との信用取引により、借入したうえでレバレッジの効いた投資は可能です。
ですが、一般的な借入と同様に返済期間が設けられ、REITの下落により証拠金維持率が低下すると、追加で証拠金が必要になるなどのリスクがあるため注意してください。
複利効果が得られない
REIT(リート)は、その他の投資と比較して、複利効果が得にくい構造になっています。
まず投資家から集めた資金を運用する不動産投資法人ですが、利益の90%以上を分配するなどの条件を満たすと、法人税免除が受けられます。
利益の90%以上を分配するからこそ、REITの高利回りは実現していますが、一方で投資家への還元を最優先にしているため、事業への再投資はほぼ行われていません。
そのため、複利効果を得るには投資家個人で行う必要がありますが、分配金だけで数万円クラスのREITは購入できないため、どうしても投資効率が悪くなるのです。
このように、投資で重要な複利効果が得られないため、ネガティブな印象を持つ方が多いのでしょう。
現物の不動産投資に比べて節税手段が少ない
REIT(リート)は、現物不動産への投資に比べて、節税手段が少ない点からおすすめしないと言われています。
現物不動産では物件購入や賃貸管理をはじめ、不動産運用に関わる多くの費用を経費として計上できます。
また、不動産運用の規模が大きくなり事業にまで成長した場合は、青色申告による特別控除額(最大65万円)も活用できるため、高い節税効果があるのです。
しかし、REITへの投資では分配金や売却益に対して、まず約20%の税金が発生します。
使える節税対策としてはNISA枠があり、積み立て投資枠で120万円まで、成長投資枠で240万円まで非課税となります。
とはいえ、REITではNISA以外の節税対策がほとんどないため、現物不動産と比較すると節税効果が薄いと言わざるを得ないでしょう。
信託報酬として手数料が発生する
REIT(リート)では、購入手数料をはじめいくつかのコストが発生しますが、信託報酬もその1つです。
信託報酬は運用の成功や失敗に関わらず、投資する限り払い続けなければならない手数料のため、特に長期保有をする際に重要なコストとなります。
信託報酬は一般的に0.2~0.5%程度となりますが、数%の利回りで運用するREITにおいては、大きなコストと言えます。
確かにREITは分散効果が期待できますが、複利効果が狙えないデメリットもあるため、コストとリターンのバランスを慎重に把握したうえで、投資すべきか検討しなければならないでしょう。
REIT(リート)に投資するメリット

REIT(リート)はやめとけ、おすすめしないと言われる場合が多いですが、現物不動産よりも換金しやすい点や、分散性が高い点など多くのメリットもあります。
ここからは、以下に沿ってREITに投資するメリットをご紹介するため、ぜひ参考にしてください。
現物の不動産投資よりも換金しやすい
REIT(リート)は、現物不動産に比べて換金しやすいメリットがあります。
現物不動産の場合、買い手を見つけて売却するまでに数ヵ月時間がかかるケースもあり、流動性が低いです。
むしろ、買い手が見つからず望む売却益が得られないケース、赤字覚悟で売却するケースも考えられるでしょう。
しかし、REITであれば市場においてすぐに売却が可能であり、数日あれば現金化できるのです。
市場の流れによっては下落する可能性もありますが、情勢を見極めることで値上がり益も期待できます。
そのため、できるだけ流動性が高く換金性、即金性の高い不動産投資を行いたい場合は、REITを検討してみると良いでしょう。
簡単に多くの不動産へ分散投資できる
REIT(リート)は、現物不動産投資に比べて圧倒的に少ない資金で、複数の物件に対して分散投資が可能です。
一般的に現物不動産の場合、融資を含め数千万円の資金が必要となります。
初期費用だけでも数百万円規模の資金が求められますが、REITであれば数万円から簡単に不動産投資が始められます。
また、特定の不動産だけでなく複数の物件に対して投資できるため、分散投資によるリスクヘッジ効果も得られるのです。
そのため、REITは現物不動産クラスの資金が不足している方や、分散投資による確度の高い不動産投資を行いたい方におすすめでしょう。
比較的高い利回りが期待できる
REIT(リート)は、株や債券などと比較すると、平均利回りが高めな傾向があります。
情勢やタイミングにより状況は大きく変化しますが、主な投資におけるおおよそな平均利回りは以下の通りです。
- REIT(リート):3~5%
- 現物不動産:3~8%
- 債権:1~3%
- 株(スタンダード全銘柄):約2.5%
- 株(グロース全銘柄):約0.7%
REIT固有のリスクはあるものの、上記の通り株や債券と比較すると高めな平均利回りとなります。
現物不動産と比較すると見劣りしますが、分散投資の観点を考えると、REITへの投資も1つの選択肢となるでしょう。
不動産投資法人としても、利益の90%以上を分配金に回すなどの条件を達成すると、法人税が免除される要件があるため、投資家への還元は積極的となるのです。
ちなみに、REITの分配金は基本、決算期の3カ月以内において年2回に渡って付与されます。
当然、不動産投資法人により決算期が異なるため、決算期の異なるREITに投資すると、毎月分配金の獲得も可能でしょう。
物件の管理コストが発生しない
REIT(リート)は、不動産投資法人が購入物件を運用するため、投資家は物件の管理コストが一切かかりません。
一般的に現物不動産を購入すると、物件管理や賃貸管理をはじめ、新規入居者の募集や集金、トラブル対応なども含めると不動産運用には多くの管理コストが発生します。
しかし、REITはあくまで自己資金を投資するだけで、運用そのものは不動産投資法人が行う仕組みです。
そのため、市場の動向や運営状況のチェックは必要ですが、REITであれば不動産運用の知識が無い方でも、簡単に投資を始められるでしょう。
ポートフォリオに組み込み分散性を高められる
REIT(リート)は、一般的な株式と同じような仕組みで取引が可能ですが、株や債券とは値動きのタイミングが異なります。
そのため、投資ポートフォリオにREITを組み込むことで、より分散性を高めた堅実な資産運用が可能となるのです。
REIT単体で考えても、複数の不動産に対して少額から投資可能なため、分散性を高める1つの手段として検討すると良いでしょう。
NISAを活用すれば非課税で運用できる
REIT(リート)は、現物不動産に比べて節税対策が少ないと懸念されていますが、NISAを活用すれば非課税にて投資が可能です。
NISAでは積み立て投資枠で120万円、成長投資枠で240万円が年間の非課税枠として設けられています。
つまり、年間合計360万円のREIT投資が、NISAを活用すれば非課税にて運用できるのです。
NISAは、非課税保有限度額が1,800万円に設定されているため、限度額以上の資金を運用する場合は課税対象となります。
しかし、少額から始められる点がREITの強みであるため、NISA枠でも十分に資産運用できるのです。
そのため、これからREITを検討している方の中で、まだNISAの枠が余っている方は、積極的に活用すると良いでしょう。
優待制度を受けられる場合がある
一部のREIT(リート)では、株主優待と同じように投資主への優待制度を設けている場合があります。
多くの場合は自社商品が多いですが、REITでは以下のような優待が受けられます。
- 自社製品
- 旅行券
- 宿泊ホテルの割引券
- 老人ホームの体験入居
- Jリーグ観戦チケット
- 娯楽レジャーチケット
優待制度を得るには、一定以上の口数を基準日まで保有しているか、また一定期間以上の保有していたかなどが条件となります。
どのような優待が得られるかは、不動産投資法人の公式サイトや証券取引所の銘柄詳細ページにて確認できるため、優待制度を活用したい場合は事前に調べておきましょう。
REIT(リート)がおすすめな人の特徴

REIT(リート)は、少額から不動産投資を始めたい方や。換金性の高い投資をしたい方などにおすすめです。
ここからは、以下に沿ってREITへの投資がおすすめな方の特徴をご紹介するため、検討している方はぜひ参考にしてください。
少額から多数の不動産に分散投資したい人
REIT(リート)は、少額から不動産に対して分散投資したい方におすすめです。
個人で現物不動産を購入する場合、金融機関の融資を受けたうえで、数千万円規模の資金が必要となるケースが多いです。
初期費用としても数百万円の資金が必要となるため、資金問題から不動産投資を諦めた方も多いでしょう。
しかし、REITであれば数万円の少額から不動産投資が可能なうえ、複数の物件に対する分散投資もできるのです。
確かにREITは固有の投資リスクも付きまといますが、数万円から不動産に対して、損益リスクを抑えた分散投資ができる点は非常に魅力的です。
そのため、資金面から不動産投資を断念していた方は、REITを検討してみると良いでしょう。
手間をかけず不動産投資をしたい人
REIT(リート)は、投資家から資金を集めて不動産投資法人が不動産を運用する仕組みです。
そのため、投資家はREITを購入するだけであり、新規入居者の募集や賃貸管理、物件管理などの管理コストが一切かかりません。
投資資金さえあれば、時間が無い方でもすぐに不動産投資に着手できるため、手間をかけたくない方にとって、REITは相性が良いでしょう。
換金性の高い不動産投資をしたい人
REIT(リート)は、現物不動産に比べて流動性が高いため、換金性の高い不動産投資を求める方と相性が良いです。
人気の高い都心部などであれば問題ありませんが、現物不動産では買い手が数か月以上見つからず、中々売却益を得られないケースがあります。
特に景気が悪いタイミングなどでは、不動産業界全体が低迷傾向になりやすく、中々換金できません。
しかし、REITであればREIT市場にて簡単に売却が可能であり、数日有れば現金化できるのです。
そのため、不動産投資の中でも特に換金性の高い投資を探している場合は、REITがおすすめでしょう。
短期間での不動産投資を求める人
REIT(リート)は、換金性の高さから短期間の不動産投資で、利益を得たい方とも相性が良いです。
現物不動産では、35年ローンなどを組んだうえで、全て返済した後にようやくインカムゲインが得られるケースがほとんどです。
そのため、投資を始めてから収益が得られるまでに、非常に長い年月が必要となります。
一方で、REITであればREIT市場にてすぐに売買できるため、値上がり幅を利用して数日程度で収益を獲得できるのです。
とはいえ、分配金ではなく値上がり幅だけを狙ったREITは、投資ではなく投機に近いため、ハイリスクハイリターンとなる点は押さえておくと良いですね。
ほとんどのREITでは、不動産投資法人より年2回の分配金が得られるため、一定期間保有したうえで、値上がり時に売却する中期的な視点で運用すると堅実でしょう。
REIT(リート)で失敗しないための注意点

REIT(リート)は、現物不動産投資よりも手軽に始められ、比較的利回りが高いなど多数の魅力があります。
しかし、市場の影響を受けやすい点や節税のメリットが少ない点など、運用していくうえでいくつか注意点があります。
ここからは、以下に沿ってREITで失敗しないための注意点をご紹介するため、投資の確度を高めるためにも、ぜひ参考にしてください。
利回りとリスクのバランス
REIT(リート)をはじめ、投資では利回りが非常に重要であり、高いほど多くの分配が期待できます。
一方で、初年度のみ利回りが高くそれ以降は低利回りになるケース、破綻リスクが高いからこそ高利回りであるケースなども考えられます。
逆に、利回りが低いREITの場合は、得られる分配は低いものの安定感があり、長期的な還元が期待できる可能性があるのです。
このように、REITで失敗しないためには、単純な利回りの高さだけでなく、リスクとのバランスを考える必要があります。
一般的にREITでは3~5%程の利回りが平均なため、この範囲を基準に利回りのバランスを検討すると良いでしょう。
借入金比率(LTV)は30%以下が理想
REIT(リート)で失敗しないためには、借入金比率(LTV)は30%以下に抑えるべきです。
借入金比率とは、REITにおける総資産に対してどれだけ借入金があるかを示す指標であり、数値が高いほど投資リスクが高い状態と言えます。
REITに限らず、一般的に借入金比率は30%以下が鉄則とされており、それ以上に借入金額が多くなってしまうと、利息によるコストがどんどん膨らみます。
次第に利息に首を絞められてしまい、利益の確保ができない点に留まらず、最悪の場合破産にも繋がりかねません。
そのため、基本的にREITに投資する場合は余剰資金で行い、どうしても借入によるレバレッジをかけたい場合は、借入金比率を30%以下に抑えましょう。
NAV倍率の高さ
REIT(リート)で失敗しないためには、NAV倍率を計算して投資対象が割安か割高かを検討すると良いです。
NAV倍率とは、REITの1口あたりの市場価値が、1口あたりの純資産額(保有不動産資産から負債を差し引いた金額)に対してどれくらいかを示します。
NAV倍率は1.0を基準にしており、基準よりも高ければ割高であり、低い場合は割安と判断されます。
一見すると割安なREITはお得なように見えますが、今後の下落が予想されているからこそ、NAV倍率が低い可能性もあるのです。
あくまでNAV倍率は投資対象の現状を示す指標なため、他の注意点と合わせてREIT銘柄の判断材料にすると良いでしょう。
ちなみに、純資産については不動産投資法人の公式サイトなどで確認できるため、REITに投資する際はチェックしておくのがおすすめです。
信用できる格付けであるか
REIT(リート)で失敗しないためには、投資対象が信用できる格付けであるかを確認すべきです。
格付けとは、第三者法人によりREITが債務不履行を起こす可能性がないか、評価したもので最も高い格付けがAAA、最も低い評価がDとなります。
格付けは不動産投資法人の保有不動産の品質、収益の安定性やレバレッジコントロールなど、様々な視点から評価されます。
当然、格付けが高いREITほどリスクが低く、安定した利回りが期待できると言えますが、例外もあるため、やはり他の基準と合わせた判断が必要となるでしょう。
ちなみに格付けは不動産投資法人、第三者法人の公式サイトなどで確認できるため、REITに投資する前の把握がおすすめです。
投資対象を確認する
REIT(リート)で失敗しないためには、市場の評価や値動きだけでなく、実際の投資対象も確認しておくべきです。
不動産投資は株や債券とは異なり、投資対象の種類やエリアなどにより、収益の安定性が大きく異なります。
例えば、投資対象の使用用途が宿泊施設なのか商業施設なのか、オフィスビルやレジャー施設なのかにより、REITの安定感は当然違います。
具体的な住所や名称までは確認できませんが、不動産の種類やエリアはもちろん、物件数や稼働率などは把握できるため、REITに投資する前には必ずチェックしておきましょう。
節税のメリットが少ない
REIT(リート)は、現物不動産に比べて節税効果が少ないため、節税効果を期待した投資はおすすめしません。
REITでは、分配金や売却益に対して約20%の税金が発生するうえ、NISA以外の節税対策がほとんど無いのが現状です。
NISAにおいても、積み立て枠や成長投資枠を活用したとしても、非課税保有限度額が1,800万円に設定されているため、それ以上の節税対策が見込めません。
少額であればNISA枠でも十分非課税運用できますが、多額の資産運用を検討している場合は、REITが節税において不向きである点を予め理解しておきましょう。
REIT(リート)はやめとけ・おすすめしないの結論

REIT(リート)は、少額から複数の不動産に投資できる点や比較的利回りが高い点など、多くの運用メリットがあります。
一方で、元本割れリスクやレバレッジが効かない点をはじめ、複利効果が得られない点や節税効果が薄い点など多くのデメリットがあるのも事実です。
そのため、REITに資産を集中させて投資する場合は、やはりおすすめできません。
しかし、REITは複数の不動産に投資できる分散性に加え、株や債券とは異なる値動きをする性質があります。
これらの特筆点を活かしてポートフォリオに組み込めば、より安定した資産運用が期待できるのです。
つまり、REITは単体ではなく他の投資と併用することで、リスクを抑えメリットを最大限活かせるため、余剰資金を使ってポートフォリオに組み込んでみてはいかがでしょうか。
REIT(リート)はやめとけ・おすすめしないに関するよくある質問